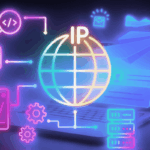UX/UIデザインの“グローバル視点”が求められる理由
UX(ユーザー体験)やUI(ユーザーインターフェース)デザインの現場では、近年ますます「グローバル視点」が不可欠になっています。
その背景には、プロダクトやサービスの設計基準が「海外トレンド起点」であることが多いという事実があります。実際、日本で人気を博しているアプリやWebサービスの多くは、海外、特に欧米や中国からの輸入が多いことをご存じでしょうか?
たとえば、Notion、Figma、Airbnb、Spotifyなど、優れたUX/UIで評価されるプロダクトの多くが海外発です。
これらのサービスでは、単に“見た目”が良いだけでなく、ユーザーの行動心理や課題を的確に捉えた体験設計がなされており、日本国内でもその影響を強く受けています。
一方で、日本のUX/UIは「ガラパゴス化」や「表面的なデザイン重視」などと指摘されることもあります。ビジュアル重視のUIは整っていても、ユーザー体験にまで踏み込めていない——そんな状況が多くのプロジェクト現場で見受けられるのです。
つまり、今後UX/UIデザイナーとしてキャリアを築いていくには、日本国内だけの基準では通用しない可能性が高いということ。海外のアプローチや価値観を理解し、適応する力がますます求められています。
本記事では、日本と海外のUX/UIデザインの違いを5つの視点で比較しながら、これからのキャリア戦略に活かせるヒントをお届けします。
UX/UIは「表面」だけでなく「行動」や「感情」に着目する時代へ。日本と海外の違いを知ることで、今後の働き方やスキルの方向性が見えてきます。
日本と海外におけるUX/UIデザイナーの役割の違い
「UX/UIデザイナー」とひとくくりにされがちですが、日本と海外ではその役割・立ち位置に明確な違いがあります。
担当範囲の違い|海外では“戦略設計”まで担う
海外、とくにアメリカやヨーロッパでは、UX/UIデザイナーがサービス設計やユーザー体験の戦略レベルから関与するケースが多く見られます。

初期フェーズからユーザーリサーチ、カスタマージャーニーの設計、プロトタイプ作成、ユーザーテスト、フィードバックループまで、デザイナーがプロダクトの中核にいるのが一般的です。
一方、日本ではまだ「UI=画面デザイン」「UX=おしゃれな導線」といった誤解も根強く、仕様がすでに固まった段階で“装飾”的な役割として呼ばれることも少なくありません。
職種分類の違い|海外は職能ベース、日本は役割ベース
海外の求人では「UX Designer」「UI Designer」「Product Designer」「Interaction Designer」など、より細かく職種が分かれているのが特徴です。
担当範囲が明確で、そのぶん求められる専門性も高くなります。
一方、日本の求人では「Webデザイナー」とひとくくりにされたり、UI/UXの区別があいまいなケースも多く、実際の職務内容とのギャップに悩む人も少なくありません。
チーム構成の違い|日本は縦割り、海外はクロスファンクショナル
海外では「プロダクトチーム」として、デザイナー、エンジニア、PM、マーケターがフラットに連携するクロスファンクショナル型が一般的です。
意見を出し合い、ユーザー視点を最優先に意思決定が進むため、デザイナーの発言力も高い傾向にあります。
対して日本企業は、開発部門・営業部門・デザイン部門がそれぞれ縦割りで動くケースが多く、現場レベルではユーザーよりも社内の「決裁者視点」に引っ張られることも。
結果的に、本来目指すべき“ユーザー中心設計”が形骸化してしまうこともあるのです。
海外では「デザイナー=問題解決者」という認識が浸透しており、日本よりも職種としての価値が高く位置づけられる傾向にあります。
デザインプロセス・評価軸の違い
UX/UIデザインの現場では、日本と海外とでプロセスの重視ポイントや評価基準が大きく異なります。この違いを理解することは、グローバル対応力を高めるうえで不可欠です。
ユーザー中心設計の徹底度
海外、とくに欧米のデザインプロジェクトでは、「Human-Centered Design(人間中心設計)」の考え方が徹底されています。
たとえば、ペルソナ設計やカスタマージャーニーマップの作成は初期フェーズの必須工程として扱われ、デザインのすべての意思決定が「ユーザーの体験価値」を軸に行われます。
一方、日本では「とりあえずUIを作って、あとで直す」というように、感覚的・経験則的な進行が主流となっている現場も多く、ペルソナやカスタマージャーニーが形骸化しているケースも少なくありません。
ユーザーテストの位置づけ
海外企業は、リリース前・リリース後ともに継続的なユーザーテストを重視します。
特にインタビュー・ABテスト・ヒートマップなどを用いて、ユーザーの行動データを定量・定性の両面で収集し、すばやくUIを改善していく「アジャイルUX」が一般化しています。
日本では、ユーザーテストの予算や時間が割かれず、社内フィードバックや役職者の意見に依存して判断されてしまう場面が目立ちます。
これでは“本当のユーザー体験”が見落とされてしまいがちです。
デザインの評価軸|見た目より“成果”
海外では、デザインの成果はKPIやビジネスゴールへの貢献度で評価されることが一般的です。
「ユーザーの操作完了率が◯%向上した」「コンバージョンが◯%改善した」といった、データに基づいた成果主義が徹底されています。
一方、日本では「上司ウケがいい」「派手で目立つ」など、主観的・表面的な指標で評価される風潮も根強く、デザイン本来の目的がぼやけてしまう懸念があります。
💡グローバル視点のポイント:
「誰に、なぜ、このデザインを届けるのか」——海外では、この問いに常に立ち返る文化が根付いています。見た目だけでなく“意味”を問う姿勢が、プロダクトの質を大きく左右します。
なぜ海外トレンドを“後追い”する日本企業が多いのか
UX/UIデザインに限らず、日本のIT業界全体が「海外の成功事例を参考にしてから動く」という傾向が根強くあります。特にデザイン領域ではその差が顕著で、数年遅れて海外トレンドを取り入れるといった後追いスタイルが一般的です。
意思決定のスピードと構造の違い
海外企業、とくにスタートアップやプロダクト主導の企業では、UXデザイナーやPMが現場の課題に即した意思決定をスピーディに実施できます。
対して日本企業では、多層的な承認プロセスが存在し、UX改善の提案も「上に説明して承認を得る」ための資料作りに多くの時間がかかります。
こうした構造が、ユーザー起点での柔軟な対応を阻む一因になっているのです。
前例主義と「失敗しないこと」が重視される文化
日本企業では、「今までうまくいっていた方法」を踏襲する傾向が強く、新しいチャレンジや仮説検証に消極的になりがちです。
UX改善の仮説も、「根拠はあるのか?前例はあるのか?」と問われ、成果が保証されない施策は実行に移されにくいという現実があります。
結果として、海外で実績が証明された後にようやく採用される、という“後追いパターン”に陥りやすいのです。
UX教育・組織理解の遅れ
海外では、UXは「組織全体の共通言語」として認識されています。
開発者・マーケター・経営陣もUXの考え方をある程度理解しており、プロダクト成功の鍵として自然に組み込まれています。
一方、日本ではUXという言葉が浸透していながらも、その意味や重要性が正しく理解されていないことが多く、結果としてUXデザイナーが「専門家扱い」され、孤立してしまうこともあります。
📝要点まとめ:
日本企業が後追いになる背景には、意思決定の遅さ・前例主義・UX教育の遅れがある。現場の課題解決よりも、組織内の“安心材料”が優先されてしまっているのが現状です。
これからのUX/UIデザイナーが意識すべきキャリア戦略
日本と海外の違いを理解したうえで、今後UX/UIデザイナーが意識すべきキャリア戦略は明確です。キーワードは「グローバル思考」と「柔軟な実践力」。これからの時代に求められる具体的なアクションを紹介します。
英語による情報収集と発信を習慣に
UX/UI分野の最先端情報は、海外メディアや英語圏のカンファレンスから発信されることがほとんどです。
たとえば、「Nielsen Norman Group」や「Smashing Magazine」などは、業界プロもチェックしている定番情報源です。
日本語の情報だけに頼っていては、どうしても数年遅れになります。日常的に英語でのリサーチを行い、自分でもnoteやX(旧Twitter)などで発信していくことで、アウトプット力と信頼性を高めましょう。
グローバル視点をもったポートフォリオ作成
海外との違いを理解したうえで、ポートフォリオも「どこを見る人が相手か」を意識することが大切です。
たとえば、単なる画面のスクショ集ではなく、ペルソナ・リサーチ・プロセス・意思決定の流れなどを明示する構成にすることで、グローバルに通用するドキュメントになります。
海外クライアントやリモート案件でも評価される実績につながります。
副業・越境案件に挑戦して視野を広げる
フルタイムの仕事に加えて、副業やクラウドソーシングを活用して「海外案件」や「英語案件」に挑戦してみるのも非常に有効です。
最近では、UpworkやToptalといったグローバル系のマッチングサイトや、日本発のグローバル副業サービス(例:Anycrew、Offersなど)を活用することで、日本にいながらグローバル環境に身を置くことが可能です。
肩書にとらわれないスキル志向
今後のUX/UIデザイナーは、「デザイナー」という枠に収まる必要はありません。
プロダクトマネージャー、カスタマーサクセス、マーケターとの境界線が溶けつつある今、ユーザー視点でプロダクトに貢献できる“総合力”が重視されます。
「Figmaが使える」だけでなく、「仮説検証ができる」「データに基づいて改善できる」「ビジネスゴールを理解している」など、より上流・戦略フェーズに寄ったスキルを意識的に伸ばすとよいでしょう。
📌まとめ:
UX/UIデザイナーは、もはや“デザインだけ”の職種ではありません。
グローバル思考、実践力、戦略力を備えたデザイナーこそが、これからの時代に選ばれる存在です。