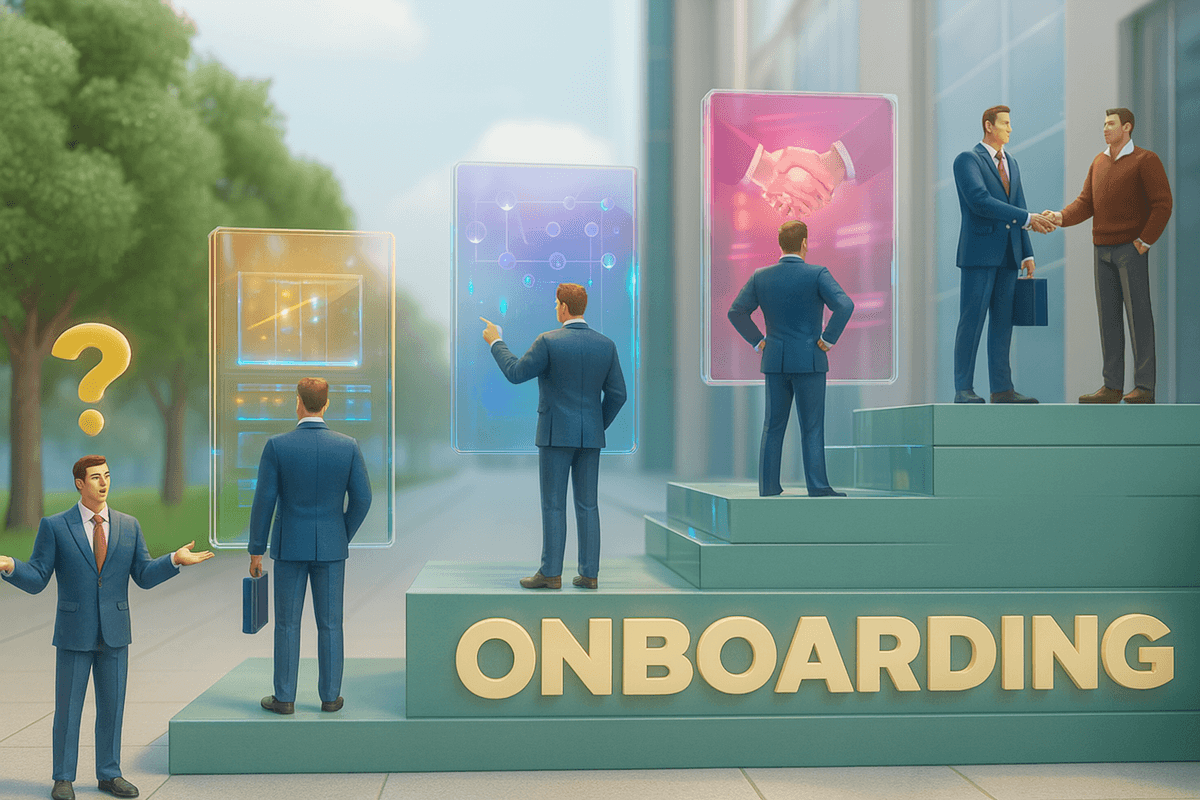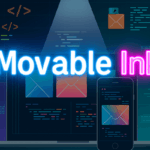オンボーディングとは?新人がすぐ辞める職場に足りないもの
「最近の新人って、すぐ辞めるよね…」 そう感じたことがあるなら、もしかするとそれは“本人の問題”ではなく、受け入れる側の準備不足かもしれません。
いま、多くの企業で注目されているのがオンボーディング。
日本語にすると「受け入れプロセス」や「定着支援」といった意味ですが、実はこれ、単なる新人研修やOJTとは違うんです。
新入社員が早く職場に馴染み、自信を持って働けるようになるまでの支援プロセス。
人事・マネージャー・メンバー全員で支える“受け入れ設計”です。
特にIT業界のようにスピード感が求められる現場では、入社してから1ヶ月が勝負とも言われます。 「放っておいたら、いつの間にか辞めていた…」なんてことも、実際にある話。
もちろん、どんなにいい制度があっても、現場の温度感が低ければ意味がない。
大切なのは「制度」ではなく、“誰が、どう関わるか”です。
この記事では、そんなオンボーディングの基本と、現場リーダーやマネージャーが実践できる工夫を実例付きで紹介していきます。
また後半では、新入社員本人が持っておくと役立つ心構えについても触れますので、職場全体で活用していただければと思います。
ありがちだけど危ない…新人を孤立させる5つの落とし穴
「ちゃんと受け入れてるつもりなんだけどな…」 それでも新人が早期離職してしまう職場には、共通する“落とし穴”があります。
しかも、その多くが“ありがち”で、つい見落とされやすいんです。
ここでは、新人を孤立させてしまいやすい5つのパターンを紹介します。 「うちも、これ当てはまってるかも…」と思ったら、少しずつでも改善してみてください。
⚠ よくある“やってしまいがち”な落とし穴5選
❶ 初日からの“放置プレイ”
「とりあえず自習しといて」で始まる初日…。
これは新人にとって地味にキツいスタートです。
最初は「どう過ごせばいいのか」「声をかけていいのか」すら分からないもの。
最初の1時間こそ丁寧にガイドしてあげるだけで、印象は大きく変わります。

❷ 誰が担当か決まっていない
「この人が面倒を見ます」と決めていないと、誰も責任を持たなくなる状態に。
新人からすると、“何かあったら誰に聞けばいいのか”が分からないのはかなり不安です。

❸ メンター制度が形だけ
名前だけの「メンター」も要注意。 定期的な面談やコミュニケーションがなければ、ただの名簿上の役割になってしまいます。
“気軽に相談できる存在”かどうかがポイントです。
❹ 忙しい現場が声をかけられない
日々の業務が立て込んでいて、「つい放置しがち」というケースも多いでしょう。
でも、新人にとっては“誰も話しかけてこない”=歓迎されてないと感じやすいもの。
「1日1声かけ」だけでも心理的ハードルはぐっと下がります。
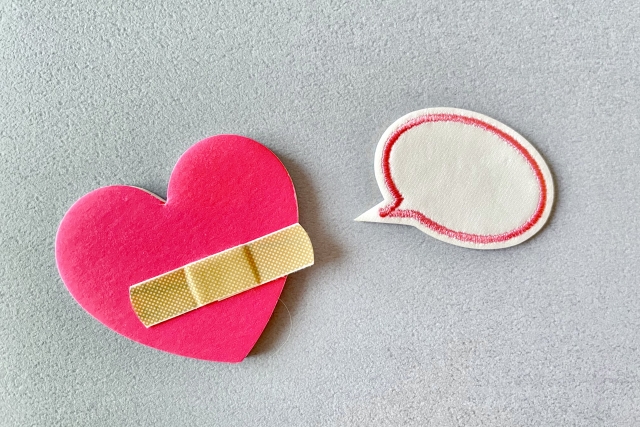
❺ 失敗を責める空気
「それ、違うよ」「なんでそんなことも知らないの?」
このような空気が漂っていると、新人は萎縮してしまい、質問も行動も消極的になります。

「失敗してOK」な安心感があるかどうかで、成長のスピードが大きく変わります。
こうした落とし穴は、どれも“ちょっとした配慮”で改善できます。
次章では、実際にオンボーディングに力を入れている企業が行っている、具体的な工夫を紹介します。
現場で効いた!辞めさせないオンボーディングの工夫5選
「制度だけ作っても、現場が動かなきゃ意味がない」 これは、多くの企業がオンボーディングに取り組む中で気づいたことです。
実際に新人の定着率を上げている企業では、“日常レベル”の関わり方にこそ力を入れています。
ここでは、筆者が実際に見聞きした、現場主導で成果を出している5つの工夫を紹介します。
ポイントは「特別なこと」ではなく、「続けられること」
少しの工夫で、辞めずに続く職場はつくれます。
① 入社前からの“軽めの接点づくり”
内定通知の後、「あとは当日よろしく!」ではなく、
Slackグループや社内報、ウェルカム動画などで“ゆるく”つながっておくと、初日の緊張が大きく和らぎます。
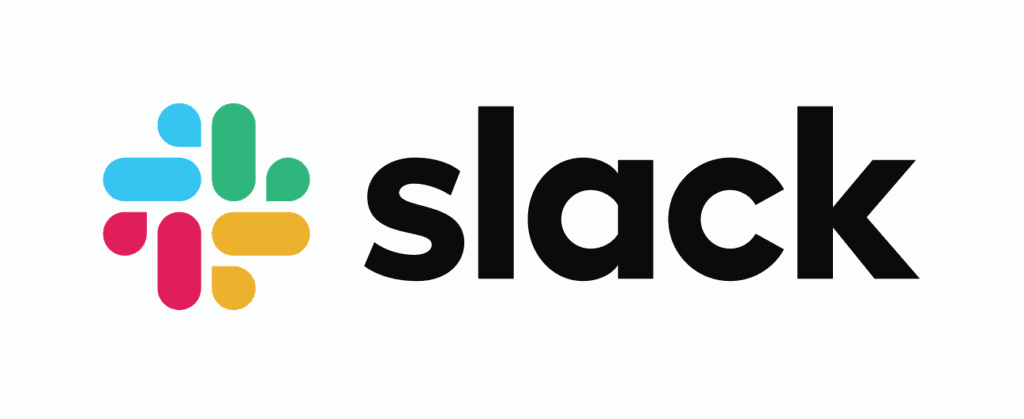
ある企業では「入社前に軽く自己紹介をお願いしたら、社員からコメントが集まってうれしかった」という声も。
「歓迎されてる」という感覚は、入社後の不安を減らしてくれます。
② 最初の1週間は“やること見える化”
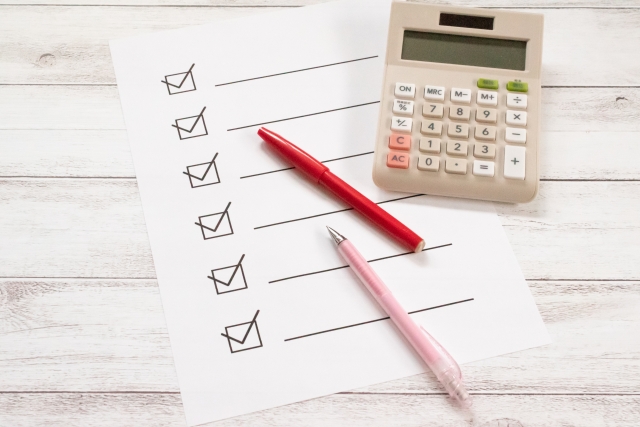
初日に紙1枚で「今週の予定」「今日やること」が共有されているだけで、新人の安心感は段違いです
「今日はこれを覚えて、明日はこれにトライする」とわかっているだけで、不安がグッと減ります。
③ 小さな成功体験を設計する
「まずはこの資料を修正してもらえる?」「昨日の内容を口頭で説明してみて」など、ハードルの低いタスクを用意しておくのも効果的。
「できた!」という感覚が、新人に自信と前向きさを与えます。

④ メンター+チームで“支える構造”に
メンター制度を導入していても、「結局、相談しづらい」では意味がありません。
チーム全体で「みんなで新人を育てる」空気感をつくることで、孤立しにくい関係性が生まれます。

⑤ 1on1の“聞き役”に徹する時間
定期的な1on1面談はあっても、上司がずっと話しているだけになってしまうケースも。
「最近どう?」「困ってることある?」と、話す機会を“渡す”姿勢が大切です。

💡大事なのは、「教える」より「気にかける」
新人にとって、最初に感じた“安心感”がその後の定着率を左右します。
次章では、実際に新人と接するマネージャー・リーダーに向けて、日常で意識したい受け入れのコツを掘り下げます。
マネージャー・リーダーが意識したい“受け入れ力”とは
「新人教育って人事の仕事でしょ?」 そんなふうに思っていたら要注意。
実際に新人が日々顔を合わせるのは、現場の上司やメンバーです。
そして、新人が「この会社でやっていけそう」と感じるかどうかは、最初に関わる“あなた”次第。
制度やマニュアルよりも大事なのは、日常のひと言、表情、リアクションです。
✅ 受け入れ力=特別なスキルではない
「教え方が上手い」とか「コミュ力が高い」とか、そんな要素よりも大切なのは、“新人を気にかけている”という姿勢。
これは誰にでもできるし、意識すればすぐに変えられる部分です。

💬 たとえば、こんなひと言が効く
- 「何か困ってることある?」
- 「ちょっと確認しておこうか」
- 「自分も最初はよくわからなかったよ(笑)」
たったこれだけでも、新人は「ここで働いていいんだ」と感じられます。
安心感=定着の第一歩です。
📌 ポイント
・自分が“評価者”にならないように
・完璧を求めず、できたことに目を向ける
・「気にしてるよ」と態度で示す
🧭 リーダー自身も“新人だった”ことを思い出す
誰だって最初は不安だったはず。
それを乗り越えられたのは、誰かが声をかけてくれたからじゃないでしょうか?
新人は環境に適応しようと必死です。
その努力を見守り、支える存在がいるだけで、辞めずに続けられる理由になります。
次は、新人本人が持っておくと役立つ「心構え」についても触れておきましょう。 受け入れる側だけでなく、迎えられる側にもできることがあります。
新人側も知っておきたい「馴染む力」って?
オンボーディングは受け入れる側だけの仕事、と思われがちですが、新人本人の“姿勢”も実は大きなカギになります。
まだ右も左も分からない中で「どう動けばいいの?」と不安になるのは当然ですが、ちょっとした心がけで、職場との距離はぐっと縮まります。
🌱 馴染む力は“ちょっと勇気を出すこと”から
たとえばこんな行動、できていますか?
- すれ違う人に自分から「おはようございます」と言う
- 分からないことを、できるだけ早めに質問する
- チャットやSlackで返事やリアクションをこまめにする

どれも簡単なことですが、「歓迎されている」と思える場づくりには、受け身ではなくちょっとだけ自分から動く姿勢が効果的です。
🔁「聞いたら迷惑かな…」より、「聞いていいですか?」
新人のうちは「こんなことで聞いてもいいのかな…」と遠慮してしまいがち。
でも、聞くタイミングを逃す方が、あとで困ることが多いんです。
周りも「聞いてくれたほうが助かる」と思っているケースがほとんど。
💡 ひと言アドバイス:
最初のうちは「ちょっといいですか?」と声をかけるだけでOK。
完璧じゃなくていい。
大事なのは“対話しようとする姿勢”です。
そして、もし職場に馴染みにくさを感じたときは、「馴染めない自分が悪い」と責めないでください。
組織にも風土があり、相性もあります。
新人にも“選ぶ権利”はあるということを忘れないでほしいなと思います。
オンボーディングは、企業・現場・本人――三者の“歩み寄り”で育っていくもの。 お互いの思いやりが、よいスタートの土台になります。